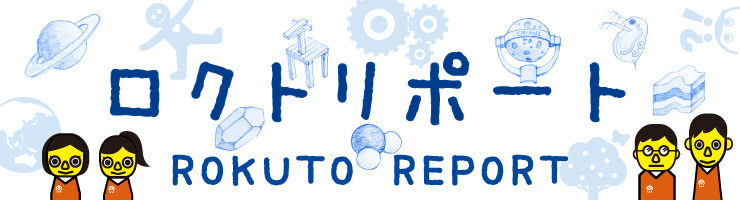立川市にある南極・北極科学館では、南極昭和基地の近くで採取した、およそ1万年前の氷を展示しています。
この氷はおよそ1万年前に降り積もった雪が押し固まったものです。
その雪が降り積もる時に風で運ばれてきた砂粒なども氷の中に閉じ込められます。
南極・北極科学館で展示している氷は少しずつとけて水になります。
この水を受け止めるお皿の中に残った砂粒を集めたものを顕微鏡で観察してみました。
昭和基地の周りの地面は黒雲母片麻岩という岩石でできていますので、氷の中には黒雲母片麻岩をつくっている鉱物の破片が砂粒として入っています。
実体顕微鏡で砂粒を観察すると、黒雲母、長石(らしき鉱物)、石英、角閃石、磁鉄鉱などがみられました。その中に金属光沢のある小さな球状の粒を発見しました(写真中央)。

(▲写真の視野幅約5㎜)
これは宇宙塵の可能性があります。

(▲宇宙塵?の幅約0.2㎜)
宇宙塵とは小さな砂粒サイズの隕石のことで、微隕石とも呼ばれます。
このような宇宙塵は地球のいろいろな所に降ってきますので、南極以外のところにもあります。みなさんの家の近くにも降っているはずです。ですから、いろいろなところで似たような金属光沢のある粒は集められます。
ただ、このような金属光沢のある球状の粒は、人間の活動(溶接など)でもそっくりなものができますので、宇宙塵なのかそうではないのかを区別するのは簡単ではありません。
しかし、一万年前の南極の氷に含まれていた球状の粒であれば、人間の活動によって作り出されたものの可能性は低く、宇宙塵の可能性が高いと考えられます。
※火山活動でも同様の粒ができることがあるため、宇宙塵であると断定するためにはきちんとした分析が必要です
【地学担当】