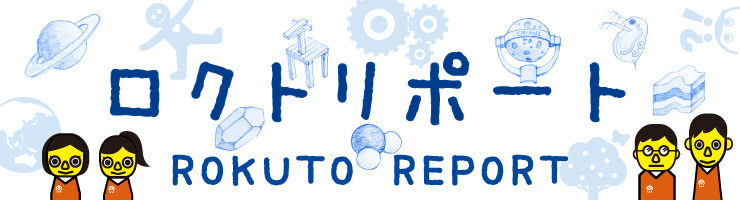西東京市にある東京大学生態調和農学機構と、市民、多摩六都科学館の三者が実行委員会形式で企画している「農と食の体験塾」大豆編、7月23日(火)に東大生態調和農学機構の圃場で第4回が行われました。以下、実行委員からのレポートです。
当日は厳しい暑さが予想されたため、前回より1時間早い8時半に集合。熱中症指数計はすでに周囲温度32.8度/湿度68.9%ということで、炎天下の作業は短時間で終わらせることになりました。
【中耕培土(ちゅうこうばいど)】
圃場ですぐに気が付いたのは、平坦だった土地に畝がきれいに作られていたこと!そして、思っていたより雑草が少ない?!実は、前回の間引き作業の後に、機構の技術職員の方が管理機を使って畝間を耕す(中耕)と同時に、土を株ぎわに寄せた(培土)ことによって、あらかた雑草も取り除かれていたのでした。

【除草】
ほとんどがイネ科のメヒシバ、他にはアオゲイトウがちらほら、端の方にかたまってカヤツリグサの仲間が生えていました。実行委員の間で「食べられる雑草」と話題のスベリヒユは、小さな小さな芽生えがたまにあるくらいでした。前日の大雨の影響でかなり土が湿っており、靴底に土がくっつき足を取られそうになりましたが、前述の中耕培土のおかげで畝間に細く道があるので作業しやすかったです。
 左から、メヒシバ、アオゲイトウ、カヤツリグサ
左から、メヒシバ、アオゲイトウ、カヤツリグサ

雑草が少なめだったとはいえ、湿った畑の土が靴底の溝に詰まって歩きにくく、作業は大変でした
【成長観察】
播種から4週間、花はまだ咲いていませんが本葉が増えて順調に育っていました。この時期、コガネムシの成虫が葉を食べることがありますが、大豆は実を食べるものなので、株自体の成長が順調であれば葉が多少食われてもそこまで気にする必要はないそうです。幸い葉の食害もほとんどありませんでした。
【五葉茶豆】
前回の観察で、大豆の本葉は、3枚の小さな葉(小葉)が集まって一つの葉を形成している複葉ということがわかりました。ただし、栽培している21種の大豆のなかで、唯一「五葉茶豆」は、成長が進むとその名の通り5枚葉になるとのこと。2週間前はほとんどが3枚葉でしたが、今回はしっかり5枚葉を観察できました。

作業中もどんどん気温が上がり、熱中症指数計は厳重警戒を示していました。酷暑が予想される8月は機構の技術専門職員の方々に管理をお願いし、圃場での実習はお休み。次回は室内で講義の予定です。