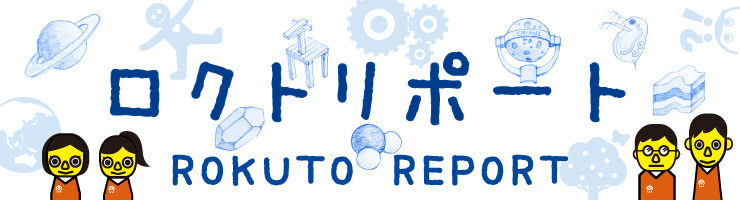西東京市にある東京大学生態調和農学機構と、市民、多摩六都科学館の三者が実行委員会形式で企画している「農と食の体験塾」。11月19日(火)は大豆の収穫の実習です。長引く猛暑の影響で枝豆の収穫は中止となりました。4か月ぶりの圃場は秋晴れの青空のもと初冬の冷たい風が吹いていました。以下、実行委員からのレポートです
<圃場のようす>
圃場は黄変した葉や緑の葉でおおわれていました。以前の実習で”大豆が順調に生長すると役目を終えた葉を落とす“と聞いていたので、大豆の成熟の様子が気になります。

品種にもよりますが、莢があまりついていないもの、莢はついているが膨らんでいないもの、莢を開けると豆が病害虫に食われているものなど、何等かの生長障害が見られる莢が目に付きます。莢に産卵し“豆”を栄養にして育つ病害虫のシンクイガの発生は、例年9月の彼岸の頃までに落ち着くそうですが今年は10月の初めころまで暑さが続いたため被害が拡大したと考えられるということです。

猛暑が続くと作物の生長に異変が起きることは一般に知られていますが、猛暑日が昨年の2倍となった今年の暑さは十分すぎたようです。(気象庁の情報では2024年の“猛暑日(35℃以上)は”約40日)。 “降れば土砂降り、晴れれば猛暑”というこの夏の傾向に、技術職員の方々は潅水や薬剤散布のタイミングなど例年にも増して気を使われたことと思います。
<収穫作業>
今回は莢がついている16品種中9品種のみ収穫しました。
収穫した品種は、比丘尼 目黒 東京八重成 小笠原在来 青梅在来 みすず 東京大豆 錫杖豆 丹波黒 鞍掛豆 日の丸大豆 借金無し 里のほほえみ すずロマン フクユタカ
収穫しなかった品種は、五葉茶豆 くるみ豆 エンレイ タチナガハ トラ大豆 馬のかみしめ です。
収穫は剪定バサミを使います。茎は太く、硬くなっていて小枝を切るような作業です。


次回の実習で行う脱穀作業を効率よく行うため、莢がついていない枝や葉を極力切り落とし、品種ごとに収穫袋に入れます。
作業のついでに根を掘り起こし根粒菌がどうなっているかを観察しました。全くついていないのもあれば大きい粒がいくつも付いている品種もありました。根粒菌を生長の栄養として使い切っていない場合、最適な環境条件が用意されれば今後もさらに生長し続けるのでしょうか?興味深いです。
<乾燥室に運ぶ>
収穫が終わった段階で、収穫袋を北のキャンパスの乾燥室に運びました。ひとつ20㎏ほどの袋の上端に紐を付けて竿に吊るし3週間乾燥させます。

次回の実習は「脱穀」です。どのような豆がどのくらい収穫できるのか出来栄えが気になります。
“地球規模の気候変動”による農作物への影響はホットな話題ですが、それは遠い国、遠い町の話ではなく、西東京の1アールの圃場にも例外なく現れていることを実感しました。