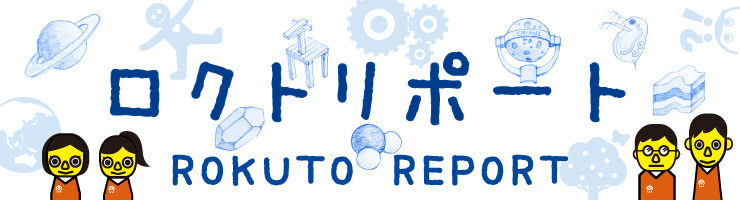参加された皆さまから大変多くの質問をいただき、講演会の時間中に全てにお答えすることができませんでした。ですが、安藤先生のご厚意により後日多くの質問にお答えいただきましたのでこちらにQ&Aを掲載します。
興味深い質問と回答ばかりですので、講演会にお越しでない皆さまもぜひご覧ください。
それでは、長くなりますがどうぞお付き合いくださいませ♪
目次
①金星の大気について
②金星探査について
③データ観測・解析について
④先生に聞いてみたいあれこれ
①金星の大気について
Q, 金星の大気に他の惑星と比べて硫黄の成分が多いのはなぜでしょうか?
A, 理由の一つとして、活火山が爆発して硫黄系のガスがどんどん出ているので硫黄がたくさん残っているという説があります。本当に活火山があるのかという点は間接的な証拠しか見つかっていないので、探査機「EnVision」などでの今後の探査で本当に活火山があるのかを調べようという取り組みもあるようです。
Q, CO₂より硫酸の方が重い気がするのですが硫酘の雲が上空50kmより上(CO₂主体の大気層の中で比較的高いところ)に漂っているのはなぜですか。
A, 「硫酸の雲ができる=硫酸蒸気(気体)が凝結(液体になる)する」
これには気温が低くないといけません。高度50kmあたりでは気温が高く、硫酸の液滴は全て蒸発してしまいます。高度が高くなると気温が下がり、硫酸蒸気が凝結して液滴になれるので、雲が発生できるというわけです。
重い・軽いというのは確かにそうですが、実際には気温や気圧が大きく関係しているのではないかと考えます。
Q, 金星の大気はなぜ多い状態で保たれているのですか、太陽風に吹き飛ばされたりしないのですか。
A, 大気の主成分であるCO₂は重たいので簡単には吹き飛ばされません。また、「太陽風により大気が散逸する」ということは起こりますが、金星は重力が大きいので大気が逃げようとしても重力が引っ張るので簡単には逃げていきません。
ちなみに、火星の場合は重力が軽いので(金星と同じCO₂が主成分の大気ですが)、太陽風で簡単に持っていかれてしまいました。
そういった重力加速度の違いというのが根本にあると思います。
Q, 雲の中の道の紫外線吸収物質が硫黄系だと推測されているのは、硫酸雲だからですか?
A, その通りです。
「硫酸(H₂SO₄)の雲の中」ということは硫黄(S)が入った物質であるだろうと考えられます。実際に行って採集するしか正体を知る方法が無いので、その点で探査機「ダビンチ」ではこちらを探る目的もあるようです。
Q, 金星で虹が見えるとしたら、地球と同じようなものが見えるでしょうか。
A, 水が全然無いので、多分虹は見えないのではないかと思います。
そういう意味では見つけたらノーベル賞ものではないでしょうか(笑)。NASAやESAは、このようなある種ぶっ飛んだ研究が好きなので、機会があれば聞いてみます。
Q, 硫酸の雨というのは耳にしますが、硫酸の雪というものはあり得るのでしょうか。
A, 硫酸の氷(固体)というものはありますが、温度が高すぎるので存在できず、基本的には液滴で存在すると考えています。
ただ、その辺りもまだ微妙で、ひょっとしたら高度の高いところではかなり気温が下がるので、硫酸が氷の状態で存在したり、もしくは硫酸の氷が凝結核となって雲を作っているかもという話があったりします。また、金星には水蒸気が多少なりとも存在するので、十分上の高度では地球のような氷雲があるかもしれません。
その辺りは、まだ金星の「化学」の部分が確立していないので、今後の探査に期待しています。
Q, 硫酸や二酸化炭素があるということは、酸素分子の存在もありそうな気がして、オゾン層も少しでもあるのかなと思ったのですが、オゾン層存在の可能性はありますか?
A, 金星大気の主成分は二酸化炭素なので、太陽光による光解離(紫外線などにより分子が分解されること)で一酸化炭素(CO)と酸素原子(O)ができます。酸素原子は反応性が高いため、普通に考えると酸素原子同士が速やかに結合して酸素分子が作られて、酸素分子が大量に存在しても良さそうなのですが、実際は酸素分子は計測できないほど少なく、金星科学の謎の一つとされています。
また、オゾンも計測はされていますが量としては極わずかで、地球のような膨大なオゾン層はありません。ちなみに、金星と同じく二酸化炭素が主成分の火星大気では、酸素分子が計測できるほど十分多く存在します。同じ大気組成なのに金星と火星でここまで違うのは大変興味深いことで、両者の大気中における化学過程の差異について現在も研究が盛んに行われています。
Q, 金星の地形が気候に与える影響が気になります。例えば地球で南極の気湿が極端低いのは地形と海流の影響があります。金星の地形情報の精度はどの程度になるのでしょうか。
A, ちょうどタイムリーな質問ですね。
今度行く金星探査機「EnVision」「VERITAS」はまさに金星の地形図を描こうというミッションを行います。レーダーの反射を使って超高精度に地形を調べようという取り組みです。過去に「マゼラン」という探査機でも地形情報を取っていますが、もっと鮮明な金星の地図が描けると思います。
Q, 地球と火星は偏西風のある特殊な星で、金星のような星が殆どの可能性があるとお聞きしましたが、そのような偏西風の有無の要因になる現象等原因は何かあるのでしょうか?
A, 大変鋭い質問ですね。
主な要因は自転速度です。地球の場合、赤道と極の間の気温差に伴う南北方向の大気の流れ(ハドレー循環)に惑星の自転に伴う力(コリオリ力)が働いて偏西風が作られます。しかし、金星のような自転が遅い惑星だとコリオリ力が弱いので、そのような風が作られにくいのです。そうすると、「ではなぜ金星では自転より早い大気の運動 = スーパーローテーションが生じるのか?」という質問になるのですが、これはまだ成因が分かっていません。数値シミュレーションによる理論的予想は幾つかありますが、金星には分厚い雲と大気があるため、個々の理論を検証できるほどの十分な観測データが取得できていないのが現状です。この点についても、欧米やインドなどの諸外国が行う将来の金星探査に期待です。
Q, 紫外線を観測しているとの話もあったが、紫外線と言えばオーロラを紫外線で観測するというのも行われていると思う。ちょうど太陽活動が最大になっているが、太陽からの影響は金星の高層の大気ではどうなっているのでしょうか?
A, そういうものを観測しているチームもあるのですが、地球で見えるようなカーテン状のオーロラは金星ではまだ見つかっていません。これについては私も詳しくないので、波長が合っていないだけなのか、本当に無いのかはわかりません。ただ、太陽活動度が高い時と低い時で金星の大気散逸(大気が逃げていく)の状況が違ってくるという話もあります。そう考えると、どういうときに金星の大気が一番逃げ出しやすいのかという話が、過去にどれだけ水があったかという話に直結してきます。
こういった大気散逸の話をインドの金星探査でやろうとしているみたいです。
Q,テラフォーミングなどで天体の大気組成を変えてしまおうとすると、惑星全体への影響の大きさはどれほどだと思われますか?というより、そもそも大気組成を変えてしまうというのは可能なのでしょうか?
A, 過去に、数値シミュレーションによって、二酸化炭素や雲・水蒸気が完全になくなった場合の金星地表面での気温がどうなるか理論的に考察した研究が為されており、気温がだいぶ変わると予想されています。
少し本筋から逸れますが、地球でも、海水の量や大陸と海の比率をほんの少しでも変えると、今の地球とは全く異なる大気運動が生じたり気温分布になったりすると指摘されています。なので、今の地球はそれだけ絶妙なバランスのもとで成り立っているのだと思います。
大気組成を変えるというのは結構大変じゃないでしょうか。でも、アメリカの大学の一つであるMITでは、火星で人が住めるように二酸化炭素から酸素を作り出す装置を頑張って開発しているそうです。もしこれが実現したら、ひょっとすると普通に火星で住める日が来るのかもしれません。
②金星探査について
Q, 金星ブームはなぜ起きたのですか?また、何を目的として金星観測をするのですか?
A, ブームはまだです(笑)これから起こればいいな。
やはり「あかつき」の影響が大きいのかなと思います。「あかつき」が金星に行って、金星ってこんな色々な現象があるんだということがかなり分かってきました。そういった研究者にとって”宝の山”があるぞということで、世界各国で金星のブームが起きかけているのかなと思います。
新しい金星探査では地表面がメインでして、地表面を探査することによって、過去の金星にどれだけ水があったかを調べる役割があります。実際に地表面の元素構成を調べて、「水分がこの程度含まれているから、過去の金星にはこれだけの水があったのでは」というように、なぜ金星は今このような状態になったのかを、また、太古の昔に金星に海があったのかどうかという話に決着をつけるためのミッションと聞いています。
Q, 今後予定されている探査衛星のダビンチは金星の大気の中に入っていくイラストがありましたが、実際に大気圏突入をするということでしょうか?
A, 「ダビンチ」は、実際に上空(宇宙?)からプローブ(観測器本体)を落として直接地表面に降り立って観測をする直接観測を行います。プローブには、雲の成分を測定する装置、風速計、気圧計、気温計など必要な機器を搭載しています。また、地表面を撮影して、その成分を調べるための光学機器も搭載するそうです。
ちなみに、ダビンチプローブの投下目標地点は、Alpha regioという南半球の低緯度にある台地を予定しています。
Q, GHz帯について詳しく知りたいです。MHz帯なんかもあるのですか?
A, あります。
MHz帯は皆さんの携帯電話やFM放送・アマチュア無線とかで使われている周波数帯です。また、波長によって見えるものが変わります。電波掩蔽では高度90kmよりも下を見ていますが、サブミリ波というのを使うと大気のもっと高いところの観測ができます。なので、サブミリ波観測というのも将来の金星探査のひとつと考えれらえています。そうすると、例えば高度95~100kmの物質の分布などが分かれば水蒸気がどれだけあるか、水蒸気がどうやってそこから逃げていくのかという、今現在の金星から水がどういった形で逃げているのかが分かってくるのではないかと期待されます。そこから過去に巻き戻していくと、過去にどれだけ水があったかという話に繋がるのではないでしょうか。
Q, 金星は、自転軸がひっくり返って逆回転だったように思いますが、他惑星と観測に差異がありますか?
A, はい、金星の自転は地球とは逆です。なので、金星から太陽の動きを見ると太陽は西から昇って東に沈むということになります。ただ、それが金星大気の観測そのものに影響を与えるということはありません。
Q, 金星にラジオゾンデを飛ばしてみるという思い切ったシナリオもあるのでしょうか?
A, 金星気球の話はあります。ただ、予算が無さ過ぎてまだできていません。日本では今は金星よりも月や火星に重点をおいているので中々難しいです。
Q, ダビンチは硫酸大気で腐食しないのでしょうか? / 硫酸雲が4日に1度のはやさでまわっているのに金星におりることはできるのですか?
A, 硫酸によってそう簡単に溶けたり腐食したりしない素材を使うと聞いています(すみません、詳細は把握できていないです)。また、大気は確かに4日で1周するほどの速さで運動していますが、ダビンチプローブの重量は200kg程度と結構重いので、重力の方が勝って金星地表面まで到達します。
Q, 金星探索に生物枠はありませんか…? / 大気と生物の関係があるということは生態系がどうなるかも分かったら面白いなと思いました。
A, 金星の生物学はあります。
金星に生物がいるのではないかという話はあって、高度70km程度の雲の中にバクテリアみたいなのがいるのではないかという話があります。実際、NASAなどには研究をしているグループもあるので、そういう機関に行くと生物の研究はかなり盛んに行われているので面白いと思います。
③データ観測・解析について
Q, 比較惑星学によって将来の地球の温暖化が予測できたり、予防策が作られたりするかもしれないのでしょうか?
A, 今、地球では二酸化炭素が増えており、温暖化の一因と指摘されています。また、PM2.5も話題になることがありますが、それの主成分は硫酸です。二酸化炭素や硫酸というのは、現在の金星大気を象徴するワードです。つまり、金星は地球の悲惨な未来を映し出す鏡とも言えます。地球が今すぐに金星のような過酷な環境に陥ることはないですが、地球大気中の二酸化炭素や硫酸が今後どういうレベルまで増えると金星のような状況になるのか、その分岐点を知るのに役立つと考えています。
Q, 金星の大気と地球の大気って結構違うと思うのですが、どのように地球と比較してデータ観測をいかすのでしょうか?
A, 地球や火星で見られる現象が、金星でも観測されることが良くあります(現象の細かい構造まで似ていることもあります)。このような同じ現象が個々の惑星でどのような役割を果たすのか、その共通点や相違点を知ることができれば、地球・金星・火星大気それぞれが持つ特徴に対する理解を深化させることに繋がるでしょう。
Q, 「Venus Express」から「あかつき」に変わった時にデータの誤差というか、機械が変わった個体差みたいなものは発生しなかったのでしょうか。
A, 電波掩蔽観測に限って言えば、同じ測定機器を載せていたので発生しませんでした。
④先生に聞いてみたいあれこれ
Q, 物理や地学が非常に苦手なのですが、何か考え方のコツなんかはありますか?
A, 高校の物理と大学の物理ではちょっと違いまして、高校物理は公式の当てはめゲームみたいなところがありますが、大学物理では微分積分を使ってちゃんと原理からわかるようになっています。私自身高校物理ではかなり苦しんだのですが、大学の物理では微分積分の方程式を使って公式を原理から導くので、すごく良く分かるようになりました。
Q, 漫画や小説も含めて影響を受けた作品はありますか?(当館で宇宙関係としては、図書コーナーの『宇宙兄弟』を読んでいる方が多くいらっしゃいます)
A, 実は宇宙兄弟を読んだことがありません。やっぱり宇宙・惑星に関連する研究をするなら読んだ方が良いですかね?漫画で影響を受けたのは『スラムダンク』ですね。「諦めたらそこで試合終了だよ」という言葉は研究にも通ずる部分があるのではないでしょうか。ちなみに、私はバスケではなくテニスをやっていました(笑)。
Q&Aは以上です。
質問をお寄せいただいた皆さま、ありがとうございました。
そして、担当者のわがままにお付き合いいただいた安藤先生、本当にありがとうございました。先生のさらなるご活躍と、「金星ブーム」が来るようにお祈りしております。