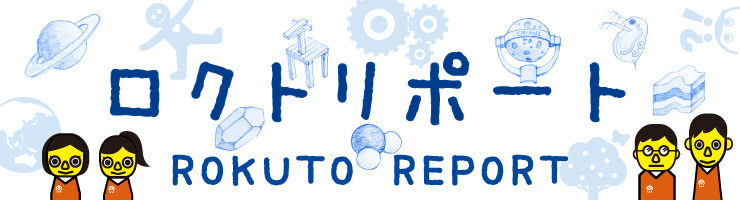参加された皆さまから大変多くの質問をいただき、講演会の時間中に全てにお答えすることができませんでした。ですが、齋藤先生のご厚意により後日多くの質問にお答えいただきましたのでこちらにQ&Aを掲載します。
興味深い質問と回答ばかりですので、講演会にお越しでない皆さまもぜひご覧ください。
それでは、長くなりますがどうぞお付き合いくださいませ♪
目次
①3種類の化学ロケット(固体ロケット・液体ロケット・ハイブリッドロケット)を比べて
②先生の研究「端面燃焼式ハイブリッドロケット」について
③ハイブリッドロケットの活用について
④先生に聞いてみたいあれこれ
①3種類の化学ロケット(固体ロケット・液体ロケット・ハイブリッドロケット)を比べて
Q, 推力の強さは?
A, 一般的にハイブリッドロケットは、固体ロケットや液体ロケットよりも推力が低い。
ハイブリッドロケットにおいては、燃料が燃焼(ガス化)する速度(燃料後退速度)を上げることが推力を上げるカギ。
Q, 一番安全なのは?
A, 一般的にハイブリッドロケットは、液体ロケットや固体ロケットよりも安全。
ハイブリッドロケットは、燃料と酸化剤を別々に搭載し、かつ、燃料を固相で貯蔵することで爆発には至りにくい。
Q, コスト面で一番安く作れるのは?
A, 一般的に、量産品ほど安くなるので新しいものを作ろうとすると高くなってしまう。
②先生の研究「端面燃焼式ハイブリッドロケット」について
<燃料の作成について>
Q, 端面燃焼式では、孔が細かく多いほど性能が高まるのでしょうか?
それとも、どこかで頭打ちになるなど、形状の最適化の余地があるのでしょうか?
A, ロケット性能としては変更しないが、ポート径が小さくなればなるほど、ポート間隔が小さくなるので、端面燃焼移行時間が短くなります。
Q, 光造成3Dプリンタでの材質はなんでしょうか?
積層の場合はABSなど使っていたような気がしますがそれらとの燃焼特性の違いあるでしょうか?
A, 光硬化性樹脂を使用しており、アクリル樹脂とほぼ同じ材質です。燃焼状態に依らず、材料によってロケット性能(特性排気速度 等)は異なります。
Q, 端面燃焼式だと燃焼中に固体燃料の穴の形が熔けて変わって効率が一定でなくなることはないのでしょうか?
A, 現在の燃料では燃焼中に燃料が溶けてしまうという現象は観測しておりません。
<ハイブリッドロケットの技術について>
Q, 爆発性の低さと燃焼の速さ以外の端面燃焼式のメリットを教えてください。 / 単一バルブで制御性が高いという点の他に、ハイブリッドロケットの機構上の安全性があるのでしょうか?
A, 燃料充填率が非常に高く(~0.98)、インジェクタが不要であるため、燃料を多く搭載できる。
燃焼面積が燃焼中に変化せず燃料後退特性から、推力制御特性が高い。
推力制御は、固体ロケットでは実現できず、液体ロケットでは燃料と酸化剤の流量制御が必要だが、ハイブリッドロケットでは酸化剤流量制御のみで実現できる。しかし、一般的なハイブリッドロケットは燃焼中に燃焼面積が変化し、燃料後退特性から推力制御中にロケット性能が変化してしまうが、端面燃焼式では推力制御中にロケット性能が変化しない。
Q, ハイブリッドロケットは燃焼室体積が大きく変動するため、燃焼室圧など計算が大変そうという印象がありますがいかがでしょうか?
A, 燃焼中の燃料後退に伴う燃焼室体積変化は、推進剤(燃料と酸化剤)質量流量変化と比較して小さく燃焼室圧力に与える影響はほぼ無視できると考えて良いと思います。
Q, 今の端面燃焼式における残課題としては何がありますでしょうか?
A, 燃焼中に燃料ポート内に形成された火炎がポート内部を急激に入り込んでしまう現象(逆火)が、高圧領域で頻発している。他にも、まだまだ問題はたくさんあります。
Q, ハイブリッドロケットの作成には何日くらいかかるのでしょうか?
A, サイズ次第では1人~10人くらいでも製造可能だと思います。
実験用の小さなものは1日でも作れるが、打ち上げ用ロケットとなると数年が必要だと思います。
<ロケット開発について>
Q,ロケットの酸化剤とはどのようなものでしょうか?
A, 燃料を酸化させる物質のこと
液体ロケット・ハイブリッドロケット:酸素(液体で保管)、亜酸化窒素等
固体ロケット :過塩素酸アンモニウム等
地上では空気(酸素)が酸化剤となりえるが、宇宙は真空(=酸素が無い)なので代わりの酸化剤をもっていかないといけない。
Q, 燃焼試験では何を見ているのでしょうか?
A, 試験目的は研究のフェーズによって変わっていきます
・燃料の溶けていく速度(燃料後退速度)
・本番と同じ動作環境(宇宙)でちゃんと作用するのかの確認 など
Q, ロケット開発の技術選択の際に、何を重視するのかという「優先度」についてどうお考えでしょうか?
A, 開発を進めるうえで、トレードオフスタディというものを実施し、定性的かつ定量的にさまざまな観点から点数化した表を作成。
宇宙開発において大事なのは「信頼性」→評価を得るためには実証することが必要
③ハイブリッドロケットの活用について
Q, 共同開発に関して、(実用例がほぼ無い中で)軌道変更用にハイブリッド式が使用されるようですが、推測でも構いませんので採用された理由について何か考えられるところはありますでしょうか。
A, 安全性と価格、ヒドラジン等の人体に有害な物質を燃料に使わない(作業面でも価格が大幅に下がる)
Q, 端面燃焼式での軌道投入用大型ロケットへのスケールアップを目指される予定はありますでしょうか
A, 私自身は行っていないが、出身研究室である北海道大学で現在研究が進められている。
Q, 人工衛星を地上に帰還させる方法について詳しく知りたいです。
A, 衛星の周回速度によって高度が決定されますので、衛星の周回速度を低下させる必要があります。比較的低軌道であれば微小な空気との摩擦によって減速していきますが、高度が高くなっていく場合には逆推力を発生させて減速させる必要があります。
④先生に聞いてみたいあれこれ
Q, ハイブリッドロケットはシステムの複雑さはあれど、安さや安全性からビジネスチャンスはありそうな気がするが、現状あまり実用に至っていない。その辺り、何か今後の見通しなどありますか?
A, 今までに多くの先生方が研究を進めてくださりましたので、次なるフェーズは宇宙実証と実用化と考えます。
まずは宇宙実証などを獲得して信頼性を高めていく必要があると思います。
Q, 将来、固体・液体ロケットからハイブリッドへの世代交代はあると思われますか?
A, 今主流の液体ロケットと固体ロケットは長く続けてきているものなので、そうなっていくためには私たちがハイブリッドロケットの未来を切り開かなければいけないと思っております。
Q, 10年、15年後の将来に向けて何か方向性などはお持ちですか?
A, 5年以内の宇宙実証をもとに、実用化フェーズに向けた調整が必要と考えております。
Q, 目標と現状とのギャップはどれほどあるのでしょうか?
A, 宇宙実証が一つの目標になりますが、そこが近いようで遠い距離間になります。
Q, 斎藤先生のご経験から、子供たちがこれから宇宙開発に関心を持って研究する道に進むためには、強い興味以外にどんな素養が必要でしょうか。
A, 色々なことに興味を持つことが大事だと思います。私自身の過去を振り返ると、そこで得た様々な縁がきっと将来に繋がっているように感じておりますので、様々な機会を得たときに「手を挙げる」ことがとても重要なのかと思います。
Q&Aは以上です。
質問をお寄せいただいた皆さま、ありがとうございました。
そして、担当者のわがままにお付き合いいただいた齋藤先生、本当にありがとうございました。先生のさらなるご活躍と、「ハイブリッドロケットの実用化」その第一歩である来年の実証実験の成功をお祈りしております。