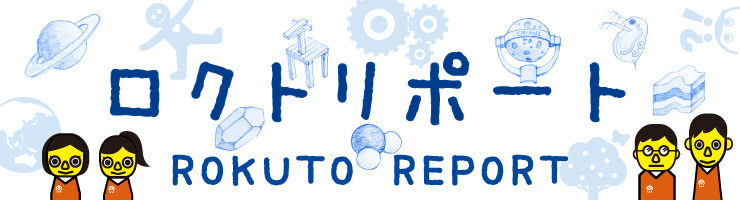長かったはずの夏休みも、もうのこりわずか。
自由研究や調べ学習の課題に取り組むみなさん、順調に進んでいますか?
「調べ学習をやってみようと思ったけど、始めかたが分からない」
「何を調べたらいいか、決められない」
「本をいっぱい借りたけど、大事なことがいっぱいでまとめきれない」
とこまっているみなさん!(&おうちのひと!)
調べ学習をどうやって始めればいいか、最初の一歩をお手伝いします。
うまく進まなくなってしまったひともいっしょにどうぞ。
かかる時間は30分くらいです!
◆ワークシートを用意しよう
こちらのPDFファイルをダウンロードして、印刷して使いましょう。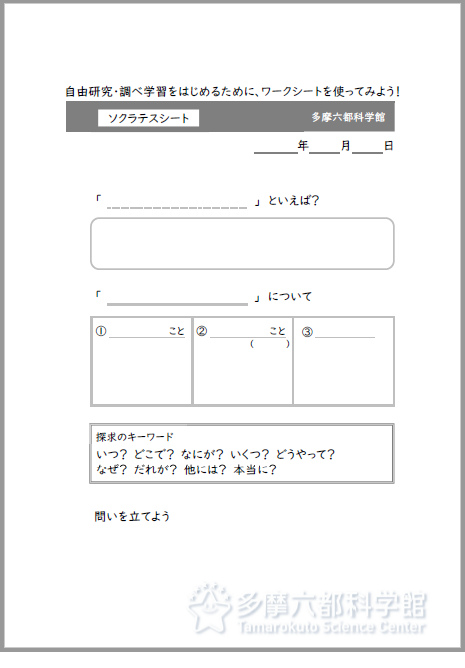
▼ここからダウンロード
多摩六都科学館ソクラテスシート
(PDFが表示されたら右クリックで保存してください)
※無断転載はご遠慮ください
◆ワークをやってみよう 1
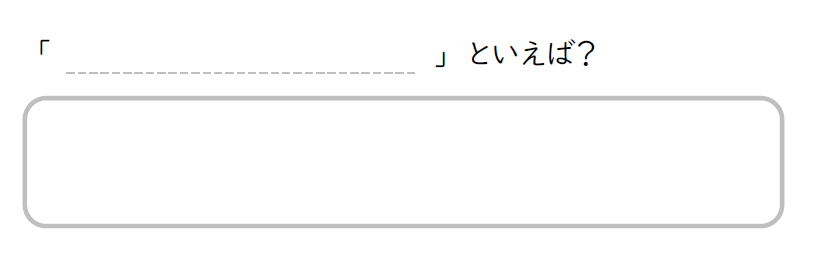 自分の調べたいことが決まっているみなさんは、点線上にそのテーマを書きましょう。
自分の調べたいことが決まっているみなさんは、点線上にそのテーマを書きましょう。
決まっていない人は、自分が調べたいことや、関心のあるテーマを書いてみましょう。
例えば、
「 宇宙・星 」といえば?
「 虫 」といえば?
「 戦争 」といえば? などなど。
テーマを書いたら、その下のわくの中に、「○○といえば?」から思いついたこと(キーワード)をどんどん書きます。
例えば、「宇宙・星」といえば? というテーマなら、
「星 太陽 木星 宇宙人 UFO 月 ブラックホール……」
とにかく、たくさん、どんどん書きましょう。
たくさんのキーワードが書けましたか?
書けたら、その中からひとつ選びましょう。
まよったら、自分が好きなものや、調べたいこと、気になることを選ぶとよいでしょう。
選んだら、次へ進みます。
◆ワークをやってみよう 2
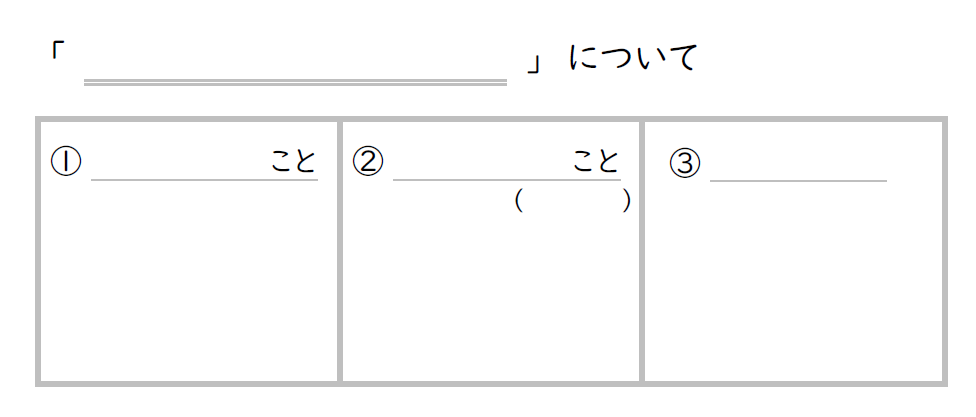 選んだキーワードを
選んだキーワードを
「_______」について
↑ここに書き入れます。
例えば、「宇宙・星」のキーワード「木星」を選んだら、
「 木星 」について
と書き入れます。
そして、その下の3つの四角の中を順番に書いていきます。
①知っていること
選んだキーワードについて、あなたが知っていることは何ですか?
知っていることをたくさん書いてみましょう。
書いたら次に進みます。
何も知らなくて何も書けなくてもだいじょうぶ。次に進みましょう。
②知らないこと(ナゾ)
選んだキーワードについて、知らないこと=ナゾもたくさんあるはずです。
知らないこと、わからないことを、どんどん書きましょう。
~あまり思いつかないときの、うらワザ~
あなたはテレビのアナウンサーや、レポーター、ユーチューバーです!
もし、生放送中に、
「いますぐ、ものしりハカセに、3つしつもんしてください!」
と言われたらどうしますか?
がんばってたくさんのしつもんを考えてみましょう。
すると、自分の知らないことがいくつか思いうかびませんか?
思いついたら、②のわくの中に書きましょう。
③ナゾの予想
最後のわくに入れるのは、
さっき自分で②知らないこと(ナゾ)に書いたナゾの答えの「予想」です。
自分で「 ? 」と思ったナゾを、自分なりに予想してみましょう。
まちがってもだいじょうぶ! どんどん予想してみましょう。
(例)「 木星 」について を考えるなら……
①知っていること
大きい 遠い 太陽けいのわく星……
②知らないこと(ナゾ)
重さ どれくらい遠いのか どんな星なのか
③ナゾの予想
重さ →地球と同じくらい?
どれくらい遠いのか →1おくkmくらい?
どんな星なのか →熱い?
さあ、ナゾが見つかりましたね! ナゾの本当の答えが気になりますね!
でも、まだ本やネットを見ないで、もうちょっとワークを続けましょう。
◆ワークをやってみよう 3
ナゾが見つかったみなさん。
そのナゾを、かっこよく書いてみましょう!
大人の研究者になったつもりで、できるだけかっこよく書きます。
だれが読んでも、ちゃんとわかってもらえるように、できるだけていねいに書きます。
(例)「木星の重さは地球と同じか?」
「木星は、地球から、どれくらい遠いのか? 1億kmくらい遠いのか?」
さらに! 他にもナゾを作ってみましょう!
ここで役に立つのが「探求(たんきゅう)のキーワード」です。
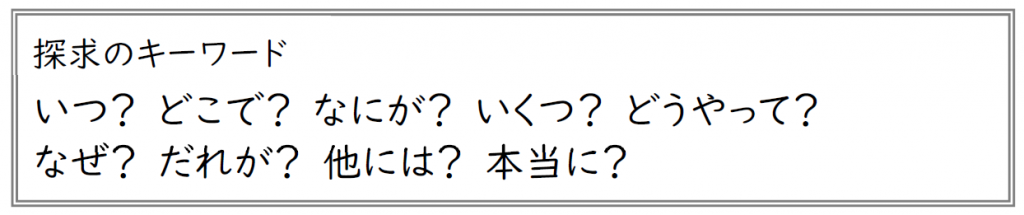
みなさんが最初に選んだキーワードと、探求のキーワードを組み合わせて、
新しいナゾを生み出してしまいましょう!
(例)木星 × いつ?
→ 木星は、いつ、できた(作られた)のか?
→ 木星は、いつ、だれに、発見されたのか?
→ 木星に、いつ、人類は行けるのか?
→ 木星は、いつ、なくなるのか?
:
:
さあ、たくさんのナゾが作れましたか?
ナゾをかっこよく書けましたか?
今みなさんがやったことをかっこよく言うと、
「問いを立てた(といをたてた)」と言います。
「木星のこと何か調べよっかな~」だけでは、
ちゃんとしたナゾになっていません。問いが立てられていません。
でも、探求のキーワードをきちんと使ってかっこよく書くと、
小学生でもちゃんと問いが立てられます。
もし、「木星のこと何か調べよっかな~」と思ったままで本や図鑑(ずかん)を見ると、
「ふーん、大きさって○○kmなんだ、へー」と読むだけで終わってしまったり、
何が大切なのかわからず、あれもこれもノートに書きたくなってしまうかもしれません。
でも、みなさんはもうだいじょうぶ。
いま考えた「問い」を手がかりに進めましょう。
「問い」のこたえを、本や図鑑で、たからさがしのようにさがして、ノートに記録していきましょう!
せっかく考えた問いは、わすれないように、
ワークシート下側の「問いを立てよう」にもメモしておきましょうね。
◆ おまけ
たくさんのナゾが見つかって、それを調べる時にも、大事なことがあります。
・ネットではなく図書館で調べる! スマホやパソコンではなく本で調べる!
ネットはとてもべんりですが、もしわざとウソが書いてあったらどうしますか?
本は、たくさんの人が、ていねいに、まちがいがないように気をつけて作っています。
ぜひ、本を使いましょう。
もしネットを使うときは、ウソのないサイトかどうか、大人の人に見てもらいましょう。
・ナゾの予想がはずれていても、消さない!
ナゾの答えを見つけられると、うれしいですよね。
でも、ナゾの答えが、自分の予想とちがっていると、少しびっくりしますね。
びっくりして、自分の答えがまちがっていると思って、消しゴムを使いたくなりますね。
でも! 消さないでください。
「自分の予想よりももっと○○だった!」というおどろきや、感想や、自分の考えもいっしょに記録した方が、とてもよい研究になります。新しいナゾが生まれたら、それも書いておきましょう。
答えを写して終わり! ではなく、世界に一つだけの、あなただけの研究記録を作りましょう!
・いつ、どこで、何で調べたかを記録する!
ナゾの答えを見つけてひとあんしん! ではなく、
本で調べたときは、①書いた人 ②本の名前 ③何ページに書いてあったか もメモ!
ネットで調べたときも ①調べた日 ②URL(http~などの文字列) を記録しましょう。
・ナゾの答えが見つからなくても、やめない!
ナゾの答えが見つからないと、こまりますよね。そんなときはこちらをチェック。
▶問いが大きすぎない?
「ブラックホールについて。」よりも、
「ブラックホールは何こあるのか?」のほうが調べやすそう。
プロの研究者でもまだ研究中のような問いは、小学生にもたぶんわかりません。
▶むずかしすぎない?
「アインシュタインの考えた特殊相対性理論とは?」はちょっとむずかしそう。
「アインシュタインという人はどんな人だったのか?」なら、小学生でも調べられるかも。
▶手がかりをさがそう
「ブラックホールの大きさはどれくらいか?」がうまく調べられないなら、
「ブラックホールのことを研究している人はだれか? どんなことをどんなふうに何を使って研究しているのか?」のように、だれかにしつ問できそうな、手がかりがつかめそうな問いに変えてみましょう。
「星の大きさはどれくらいか? どうやって調べるのか?」のように、すこしちがう問いに変える工夫もいいでしょう。
▶それでもだめなら
まわりの大人の人や、先生や、科学館の人に、何にこまっているか話してみましょう。
調べ方や、あなたの考えた「問い」について、アドバイスをもらえるかもしれません。
どんなふうにこまって、だれに相談したかもきちんと書いておきましょう。
ナゾの答えにたどり着けなかったとしても、
あなたががんばった記録は、もうりっぱな研究記録です!
それでは、みなさん(&おうちのひと)のけんとうをいのります!
よい夏休みをおすごしください。