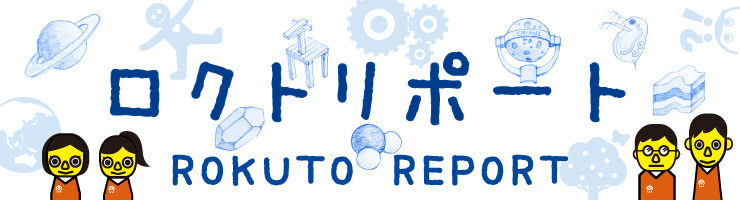当館学芸員・大平が2025年7月に「世界初の発光トビムシの新種を発見」し、その研究論文が海外の科学雑誌『Zootaxa(ズータクサ)』に掲載されました。

大平の発光トビムシの研究については、2023年8月に「ロクトの庭から光るトビムシを発見!」という記事で紹介しています。
イボトビムシの性質や、発光トビムシが光る様子が載っておりますので、こちらでご覧ください。
前回の報告から、大平はさらに日本各地を調査して、発光トビムシの新種を世界で初めて発見しました。
以下、今回発表した論文について、大平からご報告です。
——–
2023年の研究報告の記事以来、久しぶりのご報告となります。
私は「トビムシ」という、土に棲(す)む生きものを研究しています。
トビムシの仲間の姿は実に様々で、非常にバリエーションに富んでいます。私は特に、体の表面にイボをまとった「イボトビムシ科」に興味を持ち、研究を続けてきました。

このグループ(科)の中には、光を発する(発光する)種類が存在します。今回、世界で初めて発光するトビムシの新種を記載しました。
【プレスリリース】
▶ 世界初!新種の発光トビムシを発見
【掲載論文(Zootaxa)】
▶ Two new luminous species of Neanuridae (Collembola) and the discovery of bioluminescence in the genus Crossodonthina Yosii
(オープンアクセスでどなたでもご覧いただけます ※英語のみ)
私が初めてイボトビムシに出会ったのは、多摩六都科学館の庭にある雑木林でした。
そのとき、土を科学館の部屋に持ち帰って観察していると、真っ赤な体をしていて、体の表面にイボをまとった“不思議な生きもの”に出会いました。
「この生きものの名前は何だろう?」
そんな素朴な疑問から、図鑑を開いて一生懸命調べ始めました。名前を知りたい一心で探しているうちに、毎日のように通っている科学館の庭という、とても身近な場所に、まだ名前も知られていない未知な生き物がいることに、強く心を動かされました。
当時は図鑑を見ても名前を突き止めることはできませんでしたが、この“ちょっとした疑問“が、今の研究の出発点になっています。
未知なものは、私たちのすぐ足もとに転がっています。
その存在に気づくことこそが、科学を楽しむきっかけになるのではないでしょうか。
ぜひ皆さんも、自分の身の回りの環境を、いつもより一歩だけ踏み込んで観察してみてください。
きっと、思いがけない面白い発見があるはずです!
多摩六都科学館
自然グループ学芸員 大平